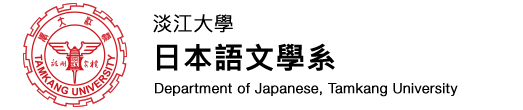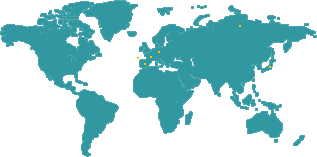私の専門は台湾史です。以前は日本統治期台湾の研究が主でしたが、ここ数年は第二次世界大戦後、冷戦下の台湾と日本の関係についても研究をすすめています。
私の専門は台湾史です。以前は日本統治期台湾の研究が主でしたが、ここ数年は第二次世界大戦後、冷戦下の台湾と日本の関係についても研究をすすめています。
この時期の台湾と日本の政治経済関係については、すでにすぐれた概説書がいくつか出版されていますが(たとえば、川島真ら『日台関係史1945-2020 増補版』)、私が現在関心を持っているのは、1960年代前半に日本で出版された台湾社会一般を論じた書籍です。1960年代前半と言えば、日本の台湾統治が終わって20年足らず、台北を臨時首都とする中華民国と日本のあいだには正式な外交関係があり、人やモノの往来も少なからずありました。しかし、この時期 の書籍の著者は口をそろえて、日本では台湾のことがあまり知られていない、正確な情報が伝わっていないと述べています。もっとも「この時期の書籍」とは言っても出版数はかぎられており、たとえば1965年出版のある本は、「戦後は台湾関係の文献はきわめて少なく、単行本としてはわずか四・五冊が市販されたにすぎない。しかも実証的な研究はほとんどといってよいほどな」(東南アジア研究会『台湾の表情』)いと述べているほどです。
学術調査や取材に制約がある時代で、出版の動機、論述内容もさまざまです。蒋介石政権の招待で台湾を訪問した評論家は、その土地改革や産業政策を高く評価し、「本省人」と「外省人」の対立(いわゆる「省籍問題」)を認識しつつも、こうした対立は遠からず解消されると楽観的な見とおしをしめしています(木内信胤『現代の台湾』)。一方で台北特派員をつとめたこともある新聞記者は、蒋介石政権の政策の問題点をきびしく批判し、省籍問題の深刻さも詳述しています(近藤俊清『台湾の命運』)。数は少ないものの、一般の読者もふれていたと思われれるこうした書籍は、当時の日本社会の台湾観の形成にどのような影響を与えていたのでしょうか。
本学科の修士課程の授業でも、学生とともにこれらの本を読みました。学部で歴史学や文学を専攻した学生はいませんでしたので、かならずしも専門性の高い議論にはなっていなかったかもしれませんが、各自が自分の思うところを積極的に発言し、他の学生と意見を交換していました。若干年配の学生が、若い学生の知らない台湾社会や台日間のできごとについて、みずからの経験を話してくれたりする場面もありました。
上掲の『台湾の表情』の冒頭に、執筆者の連名で次のような印象深い一節がしるされています(かれらは東京大学の人文地理学のゼミで台湾でのフィールドワークに参加し、卒業後は学術の道に進んだり、商社や中央官庁に勤務したりしています)。日本社会にとって台湾が遠い存在となっていたのはどうしてなのか、今日的な議論にもかかわる重要な問題だと思います。
終戦後、もう十七、八年の歳月がたつ。あれから。台湾はどう変わったであろうか。
戦争のおそろしさを幼な心にしか知らず、日本の台湾支配も、教科書の片すみに、歴史上の出来事としてしか学ばなかったわれわれも、ふと、こんな疑問をいだくことがあった。けれども、われわれのこんな素朴な疑問にさえ満足に答えてくれるものは、何もなかった……。
(2023年9月)

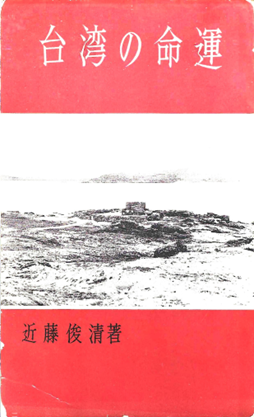
(左)木内信胤『現代の台湾』世界経済調査会、1961年。(右) 近藤俊清『台湾の命運』みすず書房、1961年。